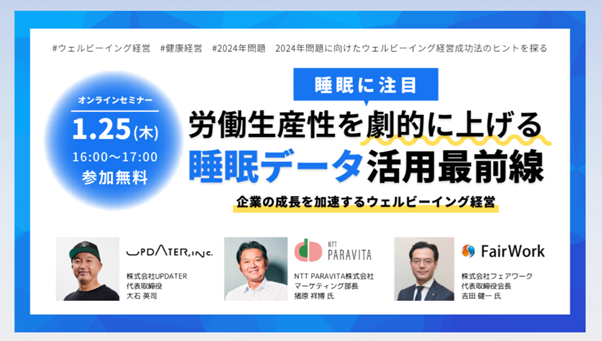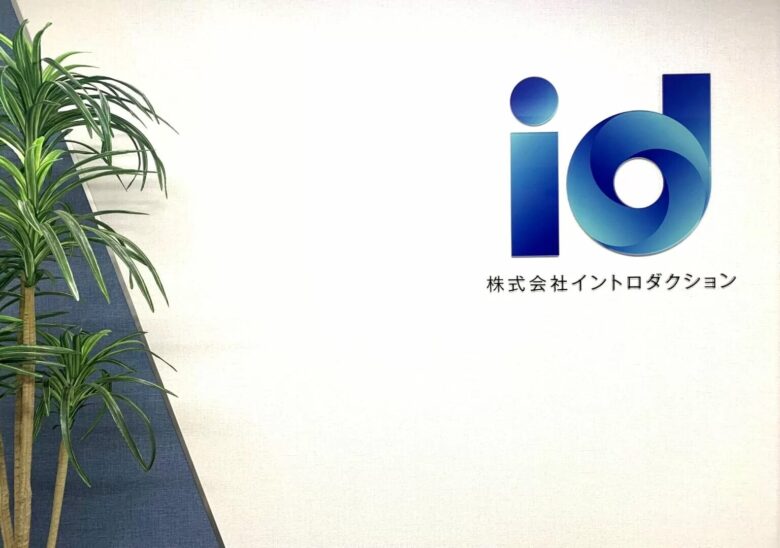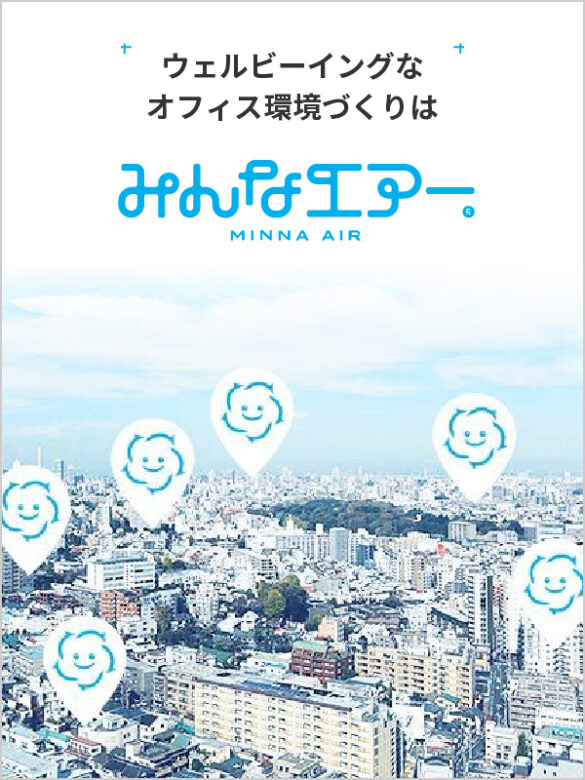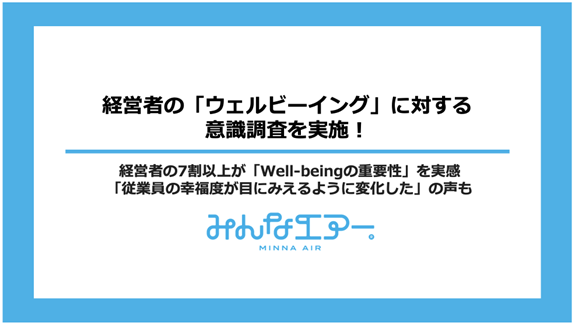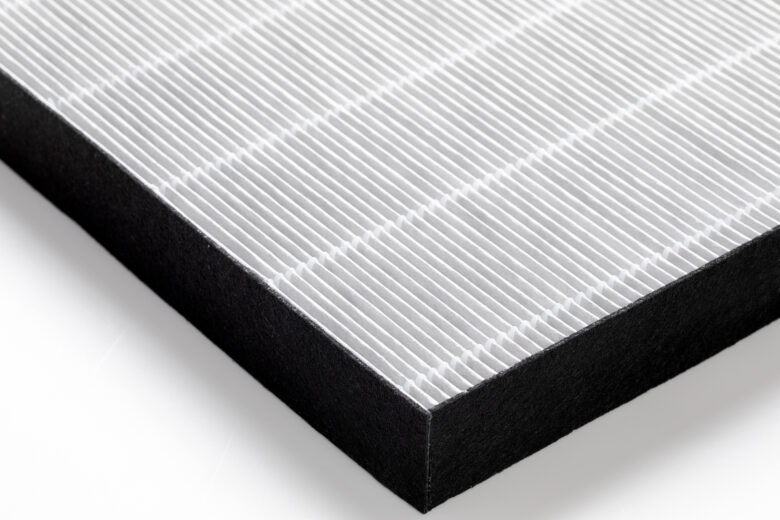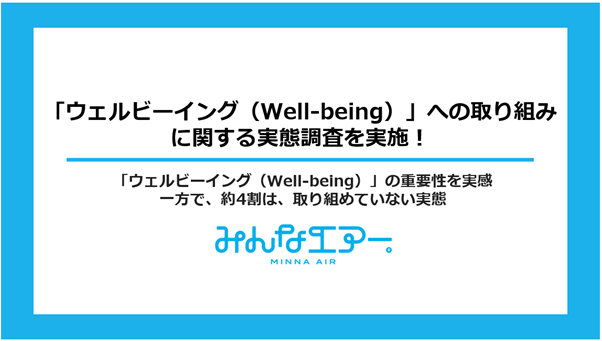千葉県佐倉市に本社を構える株式会社常磐植物化学研究所は、1949年に創業された日本で初となる植物化学の専門企業です。社会に役立つ植物成分(ファイトケミカル)の新たな価値の創造に挑戦し、医薬品をはじめ化粧品や機能性食品、食品添加物などの分野において国内外に多くの顧客を持つほか、地域貢献や環境経営に積極的に取り組んでいることでも知られています。
また、2022年には「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」の認定を、さらに2023年より同認定の「ブライト500」に3年連続で選出されています。
そんな常磐植物化学研究所の健康経営®への取り組みについて、代表取締役社長であり博士(薬科学)の立﨑仁さんと、健康経営を推進する管理本部の加藤有紗さんにお話を伺いました。
「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
自分達が「生かされている」場所だからこその地域貢献とウェルビーイング
―――まず、御社の事業についてお伺いできますでしょうか。
加藤:弊社は日本初の「植物化学」の専門企業として、植物成分の抽出・分離 精製に関する幅広いノウハウを蓄積しています。植物に関するあらゆるニーズやご要望にお応えすることを信念に、植物を原料とした、医薬品や機能性食品用途のファイトケミカル製品を製造しており、国内外の2000社を超えるお客様に製品を提供しています。
―――健康経営の体制や役割についてもお聞かせください。
加藤:健康経営に限らず、SDGs や ESG 経営を推進するにあたって、立﨑の下に方針の決定を行う「経営企画室」があり、その下に各部門・各委員会が仕組みづくりや活動の進捗管理を行い、ここで全従業員がサステナビリティ活動を実施するための体制を整備しています。健康経営においては、管理本部と安全衛生委員会が中心となって推進しており、私が舵取り役・まとめ役のような役割を担っています。
―――健康経営に取り組まれたきっかけにはどのようなものがあったのでしょうか。
加藤:実は、2019年の11月に立﨑が救急搬送されるということがあって、さらにその後すぐにコロナ禍も始まり、立﨑自身が身をもって健康の大切さを感じたというのが大きなきっかけとなっています。そして改めて「会社が元気でいるためには従業員の健康を推進していかなければならない」という思いに至り、健康経営への積極的な取り組みが始まりました。
2020年はコロナ対策がメインにはなってしまったのですが、できる限り健康経営に取り組んでいた中で「健康経営優良法人認定」というものがあると知り、この機会に挑戦することにしました。
ウェルビーイングな社会の実現に目を向けた、特色ある取り組み

佐倉ハーブ園
―――御社ならではの具体的なお取り組みをご紹介ください。
立﨑: SDGsにおける2030年までに取り組むべき目標がありますが、その先を見ていかなくてはならないという意識をみんなが持っていると思います。弊社でも「ウェルビーイングとは何か」ということをずっと議論してきたのですが、ただ言葉だけでは何も変わらないので“見える形”にしていこうという思いから、「佐倉ハーブ園」「sakuraヘルシーテラス」「SAKURAスポーツパーク」という3施設を整えました。もともとあった「佐倉ハーブ園」は心の健康・心のウェルビーイングを提供する場、「sakuraヘルシーテラス」は食を通じたウェルビーイングを提供する場、「SAKURAスポーツパーク」は体を使って汗を流してウェルビーイングを考える場ということで、この3施設から従業員のウェルビーイングはもちろん、ウェルビーイングな社会の実現に寄与していきたいと考えています。

sakuraヘルシーテラス
弊社は従業員数150人ほどの会社ではありますが、従業員だけでなく地域の皆さまにも利用していただけるこういった施設を展開しているというのは誇りであり、実際に多くの方々に足を運んでいただいています。
加藤:sakuraヘルシーテラスとSAKURAスポーツパークは2024年4月にオープンしたのですが、12月までに1万5000人を超える方々に足を運んでいただいています。

SAKURAスポーツパーク
―――短期間でそんなに多くの方が来訪されているとは驚きです。何が要因だと考えていらっしゃいますか?
立﨑:佐倉ハーブ園は入園無料ですし、SAKURAスポーツパークも一般の方でも格安の利用料で使用可能※です。またsakuraヘルシーテラスは、社員食堂を一般開放するという形なので一般の方には料金をいただいていますが※、商業的な目的ではなく、地域の皆さんや足を運んでくださった方の憩いの場になったらという思いも込めており、そういったウェルビーイングの提案というのが社会的にも理解を得られているからなのかなと思います。
※従業員は無料
―――ウェルビーイングな社会の実現への熱意、そして佐倉という地域・場所へ貢献への想いを強く感じます。
立﨑:我々の経営理念には「生かされる」という言葉が入っているのですが、会社というものは当たり前ですが土地がなければできないですし、さらに我々は化学工業として井戸水を使い、排水も出しています。だからこそ環境問題も含めて社会との関係性を大切にしていかなければならないと考えています。場所があって、地域の方がいて、お客様がいて、行政があって、どれか一つ欠けても立ち行かない。だから「我々はまわりのすべてに生かされて事業ができている」という価値観をきちんと社内で共有して、それに対して感謝の意をしっかり表現していこうと思っています。そして、我々がまさに生かされている「佐倉」という場所でまず形にしていこうという考えで取り組んでいます。
先ほど新施設に1万5000人を超える方々が足を運んでくださっていると加藤がお伝えしましたが、実は県外から来てくださる方も多くいらっしゃいます。つまりそれは我々の施設をきっかけに佐倉を訪れる方が増えているということであって、街が活性化されることにも繋げられているのではないかと思います。そして、長期的な目線では10万人まで増やしていきたいと考えています。
―――従業員の皆さんからはどのような反応があったのでしょうか。
立﨑:そうですね。驚いたのは、マルシェなど土日に行われるイベントに、従業員たちが家族を連れて遊びに来てくれることです。総勢で20~30人ほどになるでしょうか。150人ほどの規模の会社で。これってウェルビーイングの一つの形だと思うんですよね。「会社を愛している」まで重たくしなくてもいいと思うのですが、従業員にとって家族に見せたい場所・環境にはなっているのではないかと感じています。
また、このマルシェでいうと、地域の人たちへの波及も実感しています。2024年に3回行ったのですが、来場人数が初回は500人だったのが、2回目に7~800人になって、3回目には1000人を超えました。
―――どんどん増えていますね!どうやって皆さんに知ってもらったのでしょうか。
立﨑:キッチンカーや物販などの出店があるというのもありますが、やはりウェルビーイングの経営に対する価値観の共有がジワリジワリと浸透しているのはあると思います。
加藤:それに加えて SNSなどで発信もしており、フォロワーの方々が拡散してくれたり、出店者の皆さんが告知をしてくれたりすることも、多くの方に知っていただけた要因の一つです。
立﨑:皆さんがマルシェを楽しみにしてくださっているという声が聞こえてきますし、出店者の方も「マルシェは優先して出たい」と言ってくださっているようで嬉しい限りです。
―――教育への取り組みも積極的に行っていると伺いました。

教育CSRの実施 校外学習の一環
立﨑:毎年校外学習として近隣の小学校の児童が佐倉ハーブ園に来園したり、最近では幼稚園にスポーツ用品を寄付したりするなどもしています。中学校や高校ともいろいろな接点を持っていますし、地域の学校などと連携しながら働きかけていくことで、地域に貢献出来たらと考えています。採算を考えず、地域のためになるであろうことは積極的にやっていきたいと思っています。その上で、子供たちが植物や佐倉ハーブ園、弊社に興味を持ってくれたら嬉しいですね。

高校生を対象とした実験講座の風景
また、教育でいうと「佐倉サイエンスアカデミー」という、植物化学(科学)の無料講座も実施しています。これまで教育CSRはずっと佐倉ローカルでやっていたのですが、植物化学(科学)というものの魅力や面白さ、価値をより多くの方に知ってもらえるように全国に発信しようということで4年前からオンラインとのハイブリッド形式で行う「佐倉サイエンスアカデミー」を開講し、どんどん規模が大きくなってきています。

佐倉サイエンスアカデミーの様子
「食事」「運動」「働きやすい環境作り」を重視した、充実の従業員向け制度
―――従業員の皆さんのウェルビーイングで重視していることは何でしょうか。
加藤:「食事」「運動」「働きやすい環境作り」の3つを特色とした各種取り組みでしょうか。食事に関しては、先ほどの立﨑の話にも出てきましたが「sakuraヘルシーテラス」という従業員食堂を新設して、野菜たっぷりの健康的な昼食を従業員に福利厚生として無料で提供しています。それ以前は仕出し弁当だったのですが、より健康的にということで、もともと倉庫だった場所をリノベーションして施設を整えるところから取り組みました。また、我々はサプリメントに使われる植物エキスを作っているのですが、従業員の衆知を結集し、創業から75年以上にわたって研究し続けてきたエビデンス豊富な自社の植物エキスをふんだんに配合した、“社員の、社員による、社員のための”オリジナル処方のサプリメント「健康経営サプリ®」も福利厚生の一環として、社員に無料で提供するという取り組みも行なっています。

sakuraヘルシーテラス サラダバー
また、運動に関しては、50年以上前から毎朝ラジオ体操を実践しているのですが、コロナ禍で運動機会が減少してしまった中で、毎日のラジオ体操に改めてきちんと取り組むことが大切なのではないかということから、みんなでラジオ体操指導員の認定を取ろうという動きに繋がりました。毎日5分ほどの短い時間ですが、流れでやるのではなく、正しい動きを身に付けて行うことで運動量も増え、より健康に繋げることができています。これも独自の取り組みなのではないでしょうか。
さらに従業員はSAKURAスポーツパークをいつでも無料で使えるようにしています。少しでも運動の機会を作れたらという思いから、様々なスポーツが楽しめるように施設も用具も整備しており、お昼休みや定時後など、個人はもちろん部活動などでも利用することができます。
業務で他部署となかなか関わることのない従業員が部活動などに参加して新たな繋がりができたり、仲間の絆がより深まったりなど、従業員同士のコミュニケーション増加につながっているのも嬉しい点です。

―――食事、運動に続いて、「働きやすい環境作り」というのは具体的にどういったものなのでしょうか。
加藤:フレックスタイム制を導入し、個々の事情に合った働き方ができるようにしているほか、在宅勤務や時差出勤、選択的週休3日制度を取り入れています。この選択的週休3日制度は、例えば「資格取得のための勉強をしたい」「体調的に週4日勤務にしたい」など、そういった希望のある従業員が活用できるように整えている制度です。あとは副業を認めているのも特徴かもしれませんね。
―――本当に制度が充実されていて、従業員の方が羨ましく思います。(笑)
加藤:ありがとうございます。健康経営優良法人認定を申請するにあたって毎年行っている「健康習慣アンケート」というものがあるのですが、その中にある“経営陣は従業員の健康に対してよくやっていると思いますか”という項目において、80%以上が一番良い評価をしてくれています。そういった、数字でわかりやすい反応もありますし、sakuraヘルシーテラスでとても楽しそうにランチをしている様子が多く見られるのも、数字には表すことはできませんがとてもポジティブで嬉しい反応です。
経営面にもポジティブな影響を及ぼした、健康経営の推進
―――健康経営を推進したことで、経営面においてはどのような影響があったのでしょうか。
立﨑:健康経営に真剣に取り組んだ三期だけを見ても、相当上がっていると思います。もちろん、私達の機能性表示食品という製品・商品の市場とのマッチもありますが、それに取り組むのは従業員ですし、彼らのモチベーションが向上したことが売り上げにも繋がっていると考えています。
また働き方系のKPIは、女性の働き方や残業時間、禁煙施策など、すでに様々な面で改善されてきています。先ほど加藤がお話したラジオ体操の指導員認定についても取得数をKPIにしているのですが、今では90名以上の従業員が認定を受けていて、表彰もしていただきました。
―――すごい数の表彰状が飾られていますね。
立﨑:健康経営や環境経営などへの弊社の取り組みをこのように評価いただいているのは本当に光栄なことですし、これからも人や健康に関すること、環境に関することは優先順位の上位に置いて積極的に進めていこうと思っています。

健康経営などを通して価値を高め、自然と人が集まる企業に
―――様々なお取り組みが花開いて、従業員はもちろん、地域社会のウェルビーイングに繋がり、さらに経営にもポジティブな影響を及ぼし、売り上げにも反映されるというすばらしい循環が出来上がっているのではないかと感じました。
加藤:健康経営に限らず、サステナビリティや ESG 経営を進めていく中で、企業としての価値が上がってくると、自然と人が集まってくるというのを実感しています。私自身、採用業務も行っていますが、学生さんが健康経営はもちろん、それらを含めたサステナビリティの取り組みというところをすごく見ているなと感じていることもあって、そのようにポジティブな印象を抱いていただけたならとても嬉しいです。
―――最後に、これからの健康経営で目指していきたいものや実現していきたいことなどについてお教えいただけますでしょうか?
加藤:先ほども課題として挙げましたが、施設・環境の活用でしょうか。その機運を社内でより活性化していきたいと思っています。あとは、より働きやすい環境にしていく中でDX化も今後さらに重要になってくるところだと思うので、そういった多角的な部分からも健康経営に繋げて、もっと推進していけたらと思っております。
立﨑:我々にとって「健康経営」というのはウェルビーイング経営や ESG 経営の中の一つという認識です。
まずは従業員がサステナブルに働ける環境作りをしなくてはいけないというところから始まっていますが、やはり問題を掘り下げれば課題は出てくるので、それについて議論を重ねてどんどんと改善していくというのが基本です。そして、従業員がよりウェルビーイングで過ごせる環境が提供できるのであれば、それにまた投資をしていきますし、常に変化を前向きに捉えてやっていこうという姿勢を崩さずにこれからも取り組んでいきたいと考えています。
<プロフィール>
株式会社常磐植物化学研究所 https://www.tokiwaph.co.jp/
代表取締役社長 博士 (薬科学) 立﨑 仁
管理本部 人事・総務部 次長 加藤 有紗