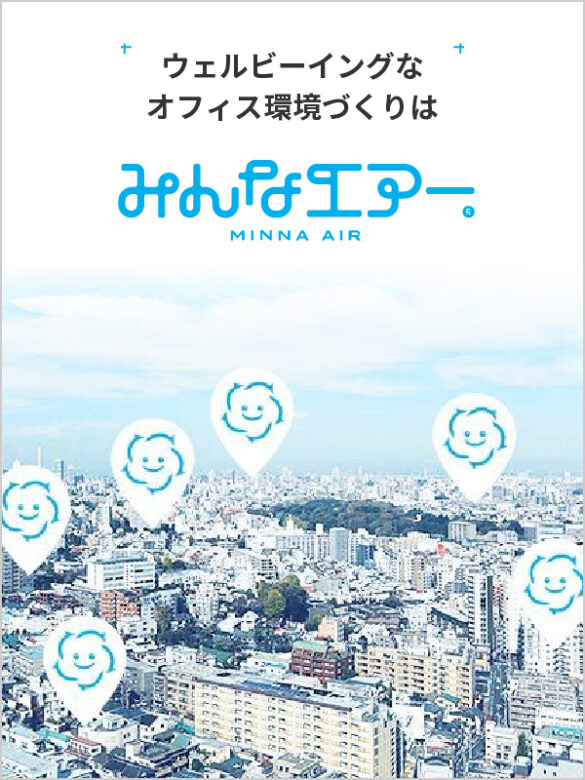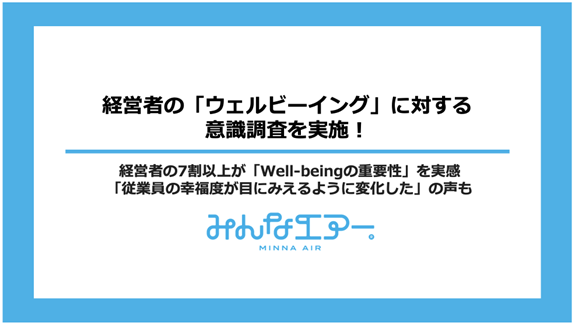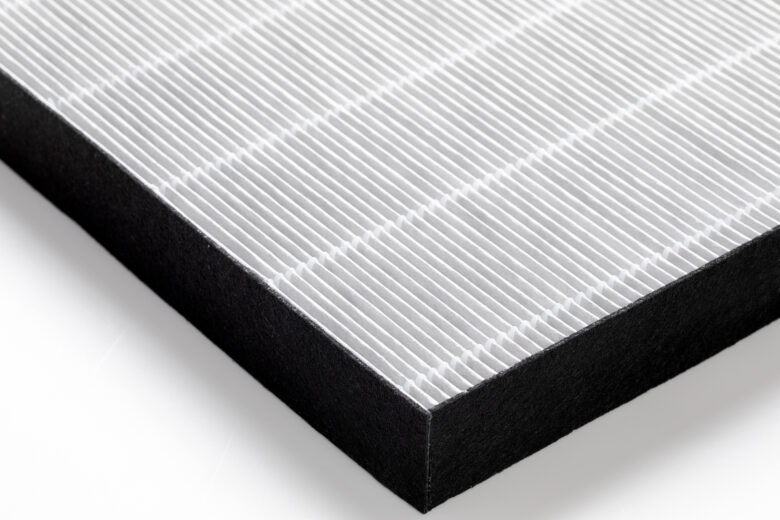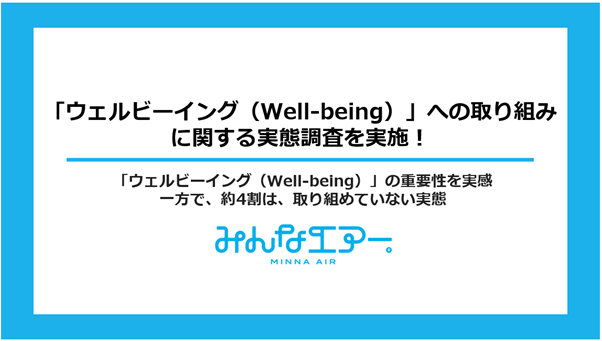東京都渋谷区に本社を置く株式会社SAKURUG(サクラグ)は、2012年に広告代理事業からスタートし、現在ではDX支援や採用支援、地方創生などの事業を展開し、多様に変わる市場に対して新しい価値を提供し続けている企業です。
「健康経営®」を積極的に実践し、これまでの「健康優良企業 ・銀」の認定や「健康経営優良法人2024」の認定取得に加え、DEI(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)推進にもいち早く取り組み、「誰ひとり取り残さない」社会の実現に向けて活動しているのも特色です。
今回は、広報業務をメインで担当しながらDEI推進室の室長も兼任している執行役員の木村杏子さん、コーポレート本部の本部長であり執行役員の大槻啓介さんに、株式会社SAKURUGが行っているさまざまな取り組みついてお話を伺いました。
「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
自社の時短勤務社員の活躍から生まれた「Sangoport事業」

執行役員 コーポレート本部 本部長 大槻啓介さん
―――まずは御社の事業について教えていただけますか。
大槻:弊社が主軸にしている事業は大きく2つありまして、1つは「QDX*コンサルティング事業」で、中身としては自社のエンジニアやプログラマー、デザイナーなどによるシステム開発やWeb制作を中心にした事業です。
*QDX: Quattro Digital Transformation、DX支援によって4つのD: Digital、Design、DEI、Dignityの発展と実現をすることを表した造語
もう1つ、力を入れて推し進めているのが専門領域のリクルーティングでして「Sangoport(サンゴポート)」という採用マッチングプラットフォームを運営しています。サンゴポートの特徴は、いわゆるDEIを推進する採用プラットフォームという点です。例えば、フルタイムはもちろん時短など子育てと仕事を両立させたい主婦・主夫の方、これまでの長年にわたって蓄積されたノウハウや経験を生かして働きたいシニア世代の方、セクシャルマイノリティの方など、性別や年齢、出身地などの境遇に関係なく、自分に合った仕事を探すための仕事紹介や、柔軟な働き方を企業側が受け入れていくための組織づくりサポートを行うことで企業様と求職者の方に満足度の高いマッチング提供を目指しています。
このQDXコンサルティング事業とSangoport事業の2つを柱としながら、他にもさまざまな挑戦を続けています。
―――Sangoport事業を始めたきっかけについて、具体的に教えていただけますか。
大槻:きっかけは、新人賞を受賞したメンバーが「新規事業立案」を任された際に挙げた100個以上のアイディアの中の1つです。もともと弊社では“時短社員”が活躍していたというのがベースにあって。実際に私が所属しているコーポレート本部では今や9割ぐらいのメンバーが時短勤務のママさんです。正直なところ、社内でスタートさせた際も上手くいくのか半信半疑な状態だったのですが、実際にやってみたら「すごくパフォーマンスが高いね!」「ものすごく会社にフィットしている!」というお声をいただき、どんどん広げていった結果がこんな人数構成になりましたが、今となっては、問題ないどころかむしろこの体制じゃないと回らないと感じるくらいです。
時短勤務だからこそ、これまで大企業や急成長企業で活躍されていた優秀な方を雇用することもできたというケースもありますし、弊社で実際にたくさんの方の活躍を目の当たりにしています。世の中にはもっとそういった高いスキルを持っていながらも働けていない人がいて、片や人材不足で悩む企業様もいらっしゃるわけで。これからもっと、こういった働き方が求められていくとともに、労働人口の減少に伴うさまざまな業界の人手不足を解決できると思ったこともきっかけとなりSangoport事業を始めました。ちなみに、最初に立案した当時新卒2年目のメンバーが、現在は執行役員として事業責任者を担っています。
―――他にも多様な事業を展開されていますが、御社ではどのように事業が生まれていくのでしょうか。
木村:弊社のビジョンとして「ひとの可能性を開花させる企業であり続ける」というものがあり、そのビジョンの実現に繋がるものを事業として行っています。
大きな方針として「2030年計画」があり、これから中長期スパンで実現していきたいことをいくつか挙げています。その1つとして「10事業30拠点」という目標を掲げていて、ゆくゆくは海外にも展開していきたいと考えています。
コロナ禍を経て、弊社代表の遠藤も、東京一極集中のようなあり方に対して考えるところがあり、“いろいろな拠点で弊社のビジョンを実現していきたい、そして地方創生にも繋げていきたい”という思いを強くしました。そのためにまずは国内の拠点を増やしていこうということで、足掛かりに和歌山県の白浜にオフィスを作り、次に仙台、福岡というかたちで徐々に拠点を増やしています。
先述の「ひとの可能性を開花させる企業であり続ける」というビジョンに則る取り組みとしては他にも、2017年より高校生インターンシップをスタートし、2023年1月には 『チェリスタ!』というエントリーサイト(https://cherista.sakurug.co.jp/)をオープンさせました。
これは高校生をインターンシップとして受け入れて、営業から新規事業の企画立案、プログラミングやWebデザインなど、社会で必要とされる仕事を体験してもらうことで、スキルを身につけてもらうと同時に、将来設計や成長機会を創出しようという取り組みです。これはもう本当に採算度外視でビジョンの実現や社会への貢献という目的で行っています。
また、『SAKURUGreenPJ(サクラグリーンプロジェクト)』も2030年計画ですね。日本の国花でもある桜の木を日本のみならず世界各地に1億本植えて育てる、そしてSAKURUGの桜が名所と呼ばれる場所を作ろうというプロジェクトです。2022年には、私どものサテライトオフィスの1拠点目がある白浜町の国立自然公園『番所山公園』に、白浜町長と一緒に植樹をさせていただいたのですが、いますこしずつ桜の木が育ってきているので花が咲くのを楽しみにしています。
―――御社の社名にも「サクラ」が入っていますよね。
大槻:「SAKURUG」という社名は、「サクラ」と「ラグ」を掛け合わせた造語なのですが、これは創業時のメンバーによるお花見でのエピソードにちなんでいます。お花見をする時期って3月下旬から4月のあたまぐらいで、まだまだ肌寒い時期ですよね。そんななかでメンバーがラグを貸し合って一緒に暖を取りながらお花見を楽しんでいる姿から、こういう温かい会社にしていきたいという願いを込めて社名としました。また、「SAKURA」というワードは外国の方にも比較的知られているので、海外に展開する際にも親しまれやすいのではないかと考えています。
木村:弊社のロゴは桜の“つぼみ”を表現していて、「これから開花していこう」という思いが込められています。
健康経営の根底にある、「家族より大事な仕事はない」という思い

―――では、健康経営優良法人の認定取得を目指されたきっかけや理由を教えていただけますでしょうか。
木村:ちょうど私が入社したタイミングの2019年には健康優良企業の「銀の認定」取得に向けて会社が動いており、同年には実際に取得することができました。やってきたことが評価されたという結果でしたが、会社がさらに大きくなっていくなかではもっと「健康経営」に力を入れてやっていかなくてはならないということで、次は健康優良法人認定の取得にチャレンジすることになりました。2024年には健康経営優良法人(中小企業部門)の認定も取得することができ、目下「ブライト500」*を取得したいと考えているところです。
*「ブライト500」とは、健康経営優良法人の中から「最も優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として、全国上位500社に選ばれたことを指します。
―――会社が大きくなっていくフェーズでは売上やコスト面などに気になってしまいがちだと思うのですが、御社の代表はなぜ「健康」というところに目を向けられたのでしょうか。
木村:創業期のベンチャーは「36協定って何?」という感じで、ゴリゴリ長時間労働というイメージが強いと思います。しかし、私たちが本当に挑戦すべき課題は「いかに長く働けるか」ではなく「いかに生産性を上げられるか」です。弊社では、代表が「家族より大事な仕事はない」と言い切っていて、社内外でつね日頃から口にしています。もちろん仕事が大好きでもっともっと仕事をしたいという気持ちは尊重したいですし、私ももっとしたいです(笑)。ですが、それによって家族を蔑ろにしてしまったり、自分自身のこころや身体のバランスを崩してしまったりするようならば、良い仕事はできません。家族を大事にするためにも、限られた時間の中でどれだけ生産性を上げられるかに頭を使い、集中する。そういった考えが会社の根底にあるからこそ、健康経営の大切さに目が向いているのだと思います。
ウェルビーイングを目指して。仕事面はもちろん、ライフサポートも積極的に

執行役員 DEI推進室 室長 木村杏子さん
―――この先「ブライト500」を目指すにあたって具体的に取り組まれていることがあれば教えていただけますか。
大槻:人事労務の統括をしている立場ですと、課題となりやすいのが勤務時間や勤怠管理の部分です。メンバーからしたら「うるさいなぁ~」と思われるくらい、残業管理の徹底を社内に周知しているところです。また、システムで残業時間が一定数を超えてきたら、アラートが本人と上長、人事チームにも通知される設定にしています。アラートが来たら残りの勤務日や業務量などを三者で相談しながら調整していくといった取り組みも行っています。
また、10年20年30年…と長く仕事をしていく上で、その過程では精神面・身体面どちらものケアが欠かせません。仕事に専念できて、かつ私生活の部分も充実できる環境をどれだけ維持できるかが重要になってくると思っているので、仕事面のサポートは当然として、できる限りライフサポートもしていきたいですね。
弊社でも産休・育児を取得するメンバーが増えてきているのですが、復帰の際に不安を感じることがないように環境や制度を整えています。具体的には、復帰前に人事チームとの面談をして不安を感じている部分などを教えてもらい、「こんなふうに準備しているからそこは安心していいよ」 「時間の制限がある中で今まで通りできないところはこうやって補填していこう」といった話し合いをする場を設けているので、不安な気持ちを減らして仕事を楽しみに思って戻ってきてもらえたのかなと思います。実際に「あれがあって安心できた」という声も聞こえていて、力を入れて取り組んできて良かったなと思っています。
―――では、これから強めていきたい部分などがあればお聞かせください。
木村:いま厚生労働省も、ライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を推進すべく、「短時間正社員」制度の導入・定着支援を行っているんです。これはワークライフバランスの文脈もそうですしウェルビーイングの実現という意味で考えたときに、すごく価値のある施策だと思っています。さまざまなライフステージの中で仕事を諦めなくてはいけなかったというケースは多くて、例えば子育て中の方の半数は仕事を続けたかったが辞めざるを得なかったと回答しているアンケート結果*もあります。
*出典元: パーソル総合研究所「ワーキングマザー調査」
だからこそ、本当は働きたかったと思っている方が仕事をすることができるのは、それ自体がウェルビーイングだと思いますし、いま現在フルタイムで働いている方においても、いつか育児や介護などの必要が迫られたとき、「短時間正社員」という制度を活用できるという安心感があることでより会社への帰属意識も高まるというふうに考えています。
いろいろな働き方の選択肢の一つとして、「短時間正社員」という制度を日本のスタンダードにしていけるように、私たち自身が今後も率先して取り組み、発信していけたらと思います。
―――「ウェルビーイング」という言葉が出てきましたが、御社の考える“ウェルビーイング”というのはどのようなものでしょうか。
木村:いちばんは「家族より大事な仕事はない」という代表の言葉を働く従業員が実現できている状態だと思います。
また、弊社は「ゼブラ企業」として成長していきたいと考えており、企業の経済的成長と社会貢献を同時に実現していくことが大事だと考えています。社会貢献を通して従業員やその家族をはじめ、お取り引きをしてくださる企業の方々、ステークホルダーの方々まで、弊社にかかわってくださるすべての方が精神的にも身体的にも健康で、物事に前向きに取り組めること、それも私どもにとってウェルビーイングな状態と言えると思います。
もともと取り組んできたことが「DEI」と合致

―――DEIという名称を掲げた部署はまだ珍しいと思うのですが、御社の中でそこを推進しよう思ったきっかけや社会的な必要性などをお聞きできますでしょうか。
木村:DEIは「ダイバーシティ(多様性)」「エクイティ(公平性)」「インクルージョン(包括性)」の頭文字をとったもので、近年ではこのDEIを推進する企業も増えています。弊社のビジョンである「ひとの可能性を開花させる企業であり続ける」ことを実現するうえで、多様なバックグラウンドを持つメンバーが個々のバリューを最大限発揮できる組織にすることが重要と考え、DEI推進室を設けました。
私はいま短時間正社員として働いているのですが、自分が出産したことによって、マイノリティ側になるという経験をしました。もちろんそれは子供がいる・いないは関係なく、環境によって誰でもマイノリティになる可能性があるという意味なのですが、その前提で組織作りを進めていくというのがとても価値のあることだと感じています。そういったところからもDEIを推進室として設け、会社としてきちんと向き合っていこうという姿勢が示されたわけです。実は、私が推進室の担当になったときはD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)っていう言葉すら知らなかったのですが、知れば知るほど弊社がもともと取り組んできたことや目指してきたものにリンクしていて、言葉として置き換えるとD&IやDEIになるよねといったかたちで、すごく自然な流れでうまれた部署だなと感じています。
長く働き続けてもらうために。将来を見据えた環境・制度づくり

―――最後に、これからも健康経営を推進することで実現していきたい社会や具体的な施策、テーマなどを教えてください。
大槻:女性社員の活躍というのは1つあるかと思います。弊社の従業員のバランスでいくと、ほぼ半々でやや女性社員の方が多いぐらいなのですが、木村もそうですけれども執行役員などの役職に就いてマネジメントをしながら実際に会社を回していくメンバーにどんどん女性社員も入ってもらえたら会社としてはすごく嬉しいし、成長にも繋がると思っています。なので、妊娠や出産、育児が障壁とならないように制度を整えることで手を上げやすい環境を作っていきたいと考えています。
木村:現在のメンバー構成としては20代と30代がボリュームゾーンなので、今は子育てとの両立支援が一番大きい課題だと思うのですが、会社が成長していく中で当然メンバーの年齢も上がっていきますから、私も含めて親の介護の問題も出てくると思います。介護との両立を考えた時に、働き方の柔軟性が必要になるという意味ではバックグラウンドが違うだけで、子育て支援と一緒だと思うんです。なので、今のうちにしっかり子育てと両立できる環境・体制を作っておけば、将来的に介護との両立などにも転用できるはずだと考えています。バックグラウンドの違いやライフステージの変化があっても、長くここで活躍してもらえるような環境作りをしていくというのも1つのテーマだと思っています。
また、サンゴポートでは「短時間正社員受け入れガイド」や「産休育休受け入れガイド」など、企業担当者の方が柔軟な働き方を推進するうえでの参考資料を無償配布しています。(https://sakurug.co.jp/news/19041/)
社会全体で多様な働き方を実現していくために、より多くの企業様にご活用いただければと思っています。
<プロフィール>
株式会社SAKURUG https://sakurug.co.jp/
執行役員 コーポレート本部 本部長 大槻 啓介
執行役員 DEI推進室 室長 木村 杏子