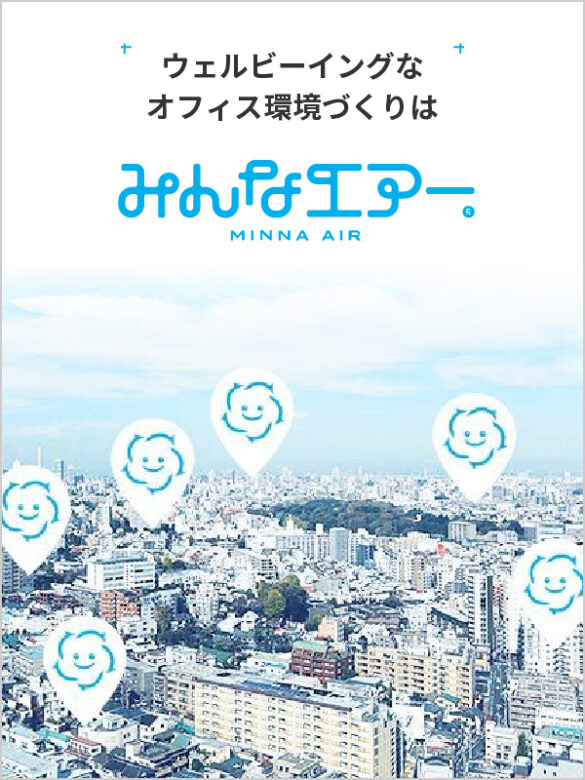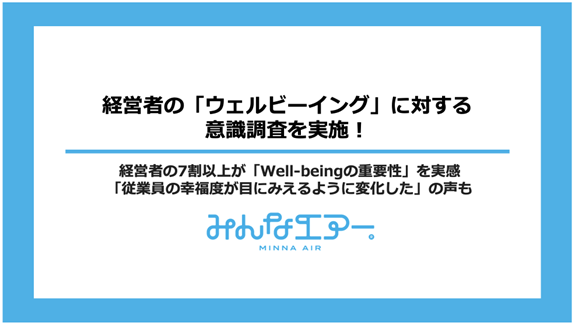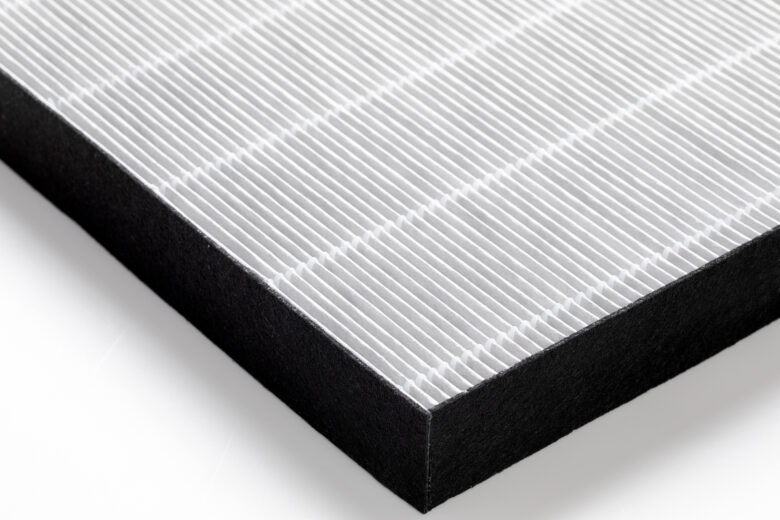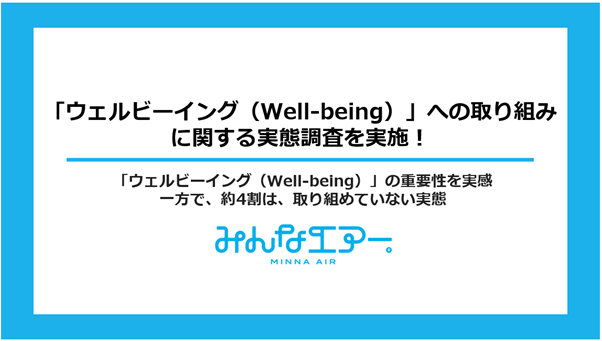東阪電子機器株式会社は大阪府吹田市に本社を構える、ものづくり企業です。モーター制御技術をコアとした電子機器のカスタマイズなどにより、創業から40年の間に、自社製品からODMまで、実に22業界1700機種以上もの開発に携わってきています。
残念ながら、私たちがその製品を直接見ることはないようなものもありますが、誰もが知る大手メーカーの多くの基盤を作っている、まさに縁の下の力持ちなのです。
経営理念は「温故創新」。経営方針では”世の中の潜在ニーズを探し形にし続ける”、“新しい事にチャレンジし続ける”、“多様性を尊重し、前例に縛られず前に進み続ける”と掲げ、社員一人ひとりが成長し、社会に貢献する企業として、世の中にHAPPY(幸せ)とWOW(驚き)を届け続けたいと社長自ら話しています。
東阪電子機器の健康経営®は、現社長である永野仁士さんが入社した2017年に本格始動。皆がHAPPYになる職場づくりと意識改革に力を入れ、2019年から6年連続取得している「健康経営優良法人ブライト500」をはじめ、「大阪モノづくり優良企業賞」「環境省 環境人づくり企業大賞 奨励賞」など多くの認証・表彰を受けています。相乗して従業員の皆さんのモチベーション、業績も共に上り調子であり、2025年4月から始まる大阪・関西万博にも出展を予定しています。そこでは、まさに経営理念をカタチにするようなワクワクさせるプランが進行中とのこと。
同社で健康経営を牽引してきた、代表取締役社長の永野仁士さんと人事総務課長の首藤あすかさんに、これまでの経緯などお話を伺いました。
「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
ポジティブに!という意識改革から始まった健康経営
―――健康経営に関する、お二方の役割からお聞かせいただけますか。
永野:まず私は会社の代表をしておりますので、“皆が気持ちよく働けるようにする”ことが1番の業務になるとは思います(笑)。
健康経営に関しては、2017年に健康経営優良法人の認定を目指すために「GET PJ」というプロジェクトをスタートさせ、私が責任者を務めました。
首藤:私は人事総務課におりまして、普段は人材の採用がメインではありますが、総務担当としてこのプロジェクトメンバーになり、永野と一緒に立ち上げからやってまいりました。
永野:私は以前、大手のメーカーにいました。この会社を創業した父の事業承継というかたちで7年前に東阪電子機器に入社したのですが、その当時私が強く感じたのは、会社として皆がいろいろと頑張って取り組んでいるのにも関わらず、従業員が自信を持っていないように見えたということでした。外部から来た僕からすると充分に頑張っているし、実績もしっかり出しているので「すごいよね!」と伝えても、皆の反応は薄かったんです。
まずは、その意識から変えていきたいと思いました。
 代表取締役社長 永野仁士さん
代表取締役社長 永野仁士さん
永野:まず、“従業員の皆が元気でHAPPYに働くために何かしたい…、何か明確な目標を立てよう!”と考えていたところに、健康経営という取り組みを見つけて、「健康経営優良法人認定を絶対に取る!メディアにも出る!」ということをすぐさま目標にしました。どちらも簡単ではないと分かっていましたが、目標を立てて達成することができれば、皆が自分たちの仕事の価値に気付くことや、“自分たちって結構イケてるんだ?”とポジティブになってくれるのではと思ったのです。それこそが健康経営のプロジェクトをスタートさせた背景なんです。
各部からメンバーを集めた健康経営チーム 「GET PJ」の立上げ
――永野さんが課題点を見つけて方針を決められたということですね。
永野:私が入社して、まずは全従業員と個別ミーティングをしました。その時に結構ネガティブなコメントがあって、会社の良いところを聞いても残念ながらあまり出てこなかったんです。このままだと、仮に私がいろいろと戦略を立てて、行動しようとしても、従業員がポジティブに挑戦してくれなければうまくいくものもうまくいかない可能性があると思いました。だからこそ、まずは心とからだを健康にすることが重要だと考え、健康経営にフォーカスすることにしました。

「GET PJ」プロジェクトのメンバー。2019年に健康経営優良法人の認定を取得した。
一番左が永野さん、左から3人目が首藤さん。
――― そのひとつとして、健康経営優良法人の認定も取得されたのですね。
永野:そうですね。健康経営を目指そうと目標を立てたときに、健康経営優良法人の認定を獲得することができれば、自己満足で終わらずに、第三者からも「この会社は健康経営ができている」と客観的な評価をしてもらえると思ったので、まずは認定を取ろうと思いました。
――― 御社のホームページを拝見すると、その他にもユニークな認証を多く取られていますね。多角的なチェックと評価を受けようというお考えですか。
永野:最初の認証を得られたときに、プロジェクトメンバーのモチベーションが明らかに上がって、自信を持ち始めたことを実感できたんです。そのことから、会社が大事にしていきたいことは認証取得など明確な目標を設定して取り組んでいくことにしました。
我々の取り組みで評価されていることには、健康経営と、あとは環境への取り組みがあります。私どもの技術による“物を動かすモーター制御”は、実は全CO2 の 40%ぐらい排出しているんです。だからこそ、出来るだけ、エネルギーを使わないものづくりを通して省エネに貢献することが大事だと考えていますし、環境にも良い取り組みに繋がっているということを第三者にも知ってもらうべきであると感じました。

これまで受け取った表彰状
――― プロジェクトの中で従業員の皆さんから好評だったり、主催者側としても面白かった取り組みはありますか。
首藤:1年に1回ぐらいのペースでウォーキング大会に参加しています。始めたきっかけは健康経営の一環としてでしたが、今ではプロジェクトを超えた会社のイベントとして定着してきましたね。各部署から参加するので部門を越えたメンバーとのコミュニケーションが増えるきっかけになって、取り入れて良かったと思う事例の1つです。
イベント会社が開催するもので、1000社くらいが参加して10日間に歩いた合計距離で競い合うという内容なんです。最低1日3000歩あるこうという基準となる目安もあって、弊社からは永野と私も含めた、20代から50代まで幅広い年代のメンバーが参加しています。
永野:皆が毎日何歩あるいたかがアプリで分かるので、急な歩数減少がみられた人に「何かあったの?」と話しかけるなど自然にコミュニケーションがとれて面白いですよ。弊社はいつも1000社中20位以内には入っています!期間中にうっかりログインし忘れると、歩いてもカウントされないので、首藤さんも土日にサポートしてくれたりしたよね。(笑)
首藤:そうですね、休みの日にも「ログインしてませんよ~」とかLINEしてます(笑)。
――― 仲がいいからこそできるコミュニケーションですね。
予防としてのメンタルヘルスケア。社内交流の場も大切
永野:大手企業では当たり前ですけど、中小企業ではまだまだ進んでいないんじゃないかと思うところでは、メンタルヘルス対策に取り組んでいます。私どもの会社では有難いことに、これまでに心の不調をきたしてしまったという人はひとりもいないんですけど、今後に向けて取り組みを始めています。メンタルヘルス疾患は誰にでも起こりうることだと思うんです。カウンセラーの先生に講演をしに来てもらって、自分でも気付かない間に心身のバランスが崩れてないかなどセルフチェックとセルフケアができるような取り組みを始めました。
あとはコミュニケーションという点で大事にしているのが、年に1回のバーベキュー大会ですね。個人的にもすごく気に入っていて、部署・部門の垣根を越えて良いですよね。全員で担当メンバーが買い出しに行ったり、野菜の皮むきなどの準備をしていると、普段おとなしい人がテキパキしていたり、逆にすごく仕事ができると思われている人もこういう時はのんびりしているんだねとかいろんな気づきがあるし(笑)、普段なかなか関わりのない部門の人たちとも話すチャンスにもなるので良い取り組みだと思っています。

管理本部 人事総務課長 首藤あすかさん
――― 健康経営を推進されてきて、従業員の皆さんの反応はいかがでしょうか。 変わってきた部分などはありますか?
首藤:進めていく上でハードルというのはなかったですが、「健康経営とは何か」という根本的な理解や、それが世の中的に重要になってきているという感覚を従業員の皆に浸透させるということに少し時間がかかったように思います。ですが外部の方と接することが多い営業メンバーなどは、「健康経営の認定を取られているのを見てお電話しました!」と言われることが増えたみたいです。健康経営の認定を取っていることがこんな風に外部からも評価されるということを実感した、とよく聞きますね。冒頭に永野が言いましたけれども、そうやって外部から評価されたり問い合わせが増えてきたりという実感があることで、従業員の意識が変わったなと思っています。
健康経営の取り組みをスタートさせて、人間関係と業績が好転
永野:今は中小企業でも多くの会社が健康経営に取り組み始めていて、それが当たり前になってきているんじゃないかとは思います。僕は健康経営って結局、従業員の人たちが楽しく、だけど頑張ることができる状態が一番良いと思うんです。それは組織を越えて、縦横も含めて良い関係になっている、もっと言えば皆が会社のことが好きになる、会社に興味を持つことだと思っていて、その点はこの5〜6年で大きく変わって良くなってきたなと感じています。
――― 健康経営を推進した結果、数値として何か変化があったものはありますか?
永野:取り組み初期からの具体的な変化の記録を取っているものはありませんが、ひとつの指標として、業績面では7年前と比べて利益が580%ぐらい増えているんですね。これは安全面や生産性が良くなったことも大きいですし、誰か一人ができないときに他の誰かがサポートするような体制・コミュニケ-ションが取れていることなどが、ダイレクトに利益に繋がっていると思っています。
――― 500%超えはすごい! 人が活性化したことによる成果ですね。 首藤さんのお取り組みもぜひご紹介いただけますか?
首藤:2024年2月、当社の41期が始まった事をきっかけにインスタグラムを始めました。これは本当に始めて良かったなと思っています。基本的に毎日私含めた2名で更新をしているのですが、毎日特別なことを載せるということは難しいので、なんてことのない日常を写真に収めて発信しているんですが、大きな気付きがありました。
私たちが会社の日常を発信するには、会社の良いところを見つけることにも繋がっているんです。発信する内容をプロジェクトメンバーだけが探すのではなく、他の部門のメンバーも気にかけてくれていて、「これインスタに載せたらどう?」という声もたくさんもらうようになりました。やり続けることで、他のメンバーとの一体感も生まれたこれも良い事例だと感じています。

日常を切り取って毎日投稿。(@tohan_denshi_kiki_co_ltdより)
人を元気にHAPPYにすることが、ウェルビーイング
――― これからの健康経営、ウェルビーイングの実現に向けて、重点的に取り組んでいきたいことを教えてください。

永野:弊社はこれまで、電子機器のカスタマイズでODMを請け負ってきて、自社商品というのはありませんでした。ですが新たに、今後は自社の商品を出していこうということになり、これまでの既存事業に加えて新しくウェルビーイング事業を立ち上げたんです。 我々らしい“ものづくり”を考えたり、海外で流行っているけれどまだ日本に入ってきていないものを日本風にカスタマイズしたりして販売するといった事業を始めています。
キーワードとして、スポーツ×テクノロジーのスポーツテックやフード×テクノロジーのフードテックなどが、ウェルビーイングの肝になってくると私は思っているので、そのような製品をこれから開発していこうと考えています。
今年の大阪・関西万博にも出展をするのですが、せっかく出展できるならドラえもんの道具を作れないかなと思っています!ドラえもんの道具に、火山などの暑い場所に行ったら涼しくなって、氷河期の世界に行ったら温かくなる「エアコンスーツ」というのがあるんです。これは今の社会課題を解決する画期的なものだから、ぜひ我々のチカラで作れないかと思い、大阪大学や神戸大学、ベンチャー企業と連携をしながら製作を進めているところなんです。

大阪関西万博に出展予定のエアコンスーツ
――― ウェルビーイングを、こういう捉え方をするのは御社ならではだなと思います。
永野:ウェルビーイングっていろんな捉え方があるとは思うんですけど、僕が会社でずっと伝えているのは、人がより元気になる、HAPPYになることにこだわろうということです。最終的には、10年後になるか20年後になるかわからないですけど、”ウェルビーイングシティ”っていうひとつの(皆が集まるコミュニティ)パークのような場所ができて、そこに行けばいろんなことができて、いろんな人と出会えて、スポーツもできて、その後には食事なんかしたりして…、ちょっと元気がなくなったときに、皆そこに行けば元気でHAPPYになれる、そんな場所を作るのが理想です。
<プロフィール>
東阪電子機器株式会社 https://tohan-denshi.co.jp/
代表取締役社長 永野仁士
管理本部 人事総務課長 首藤あすか