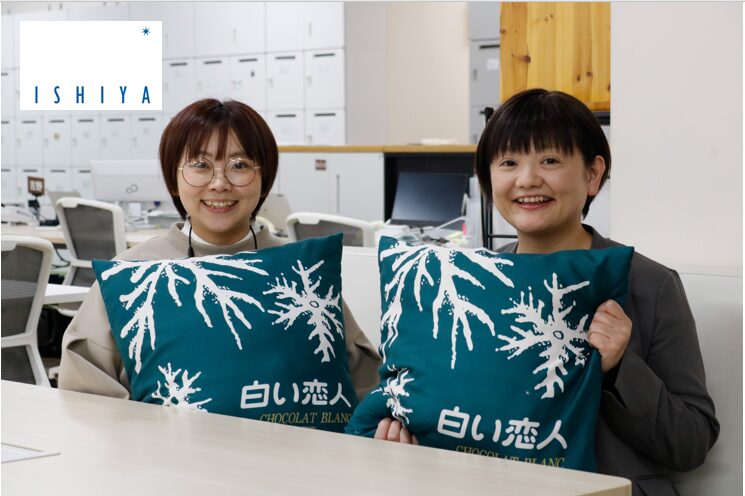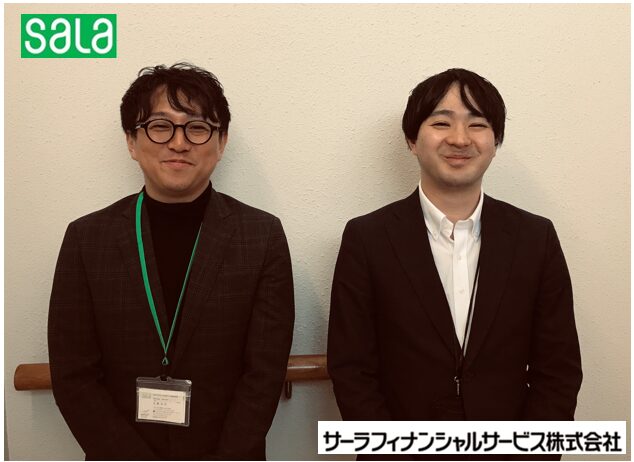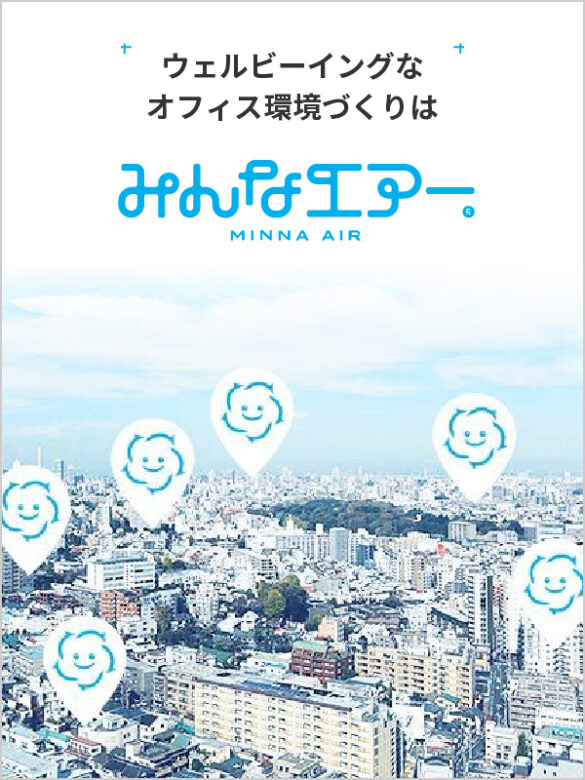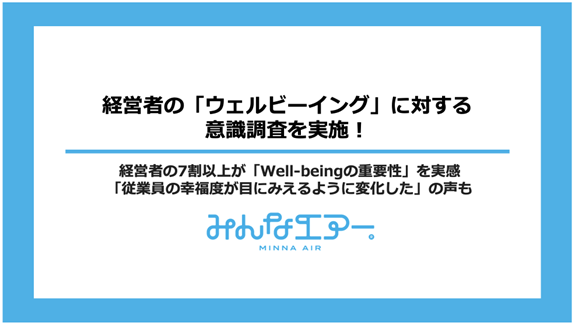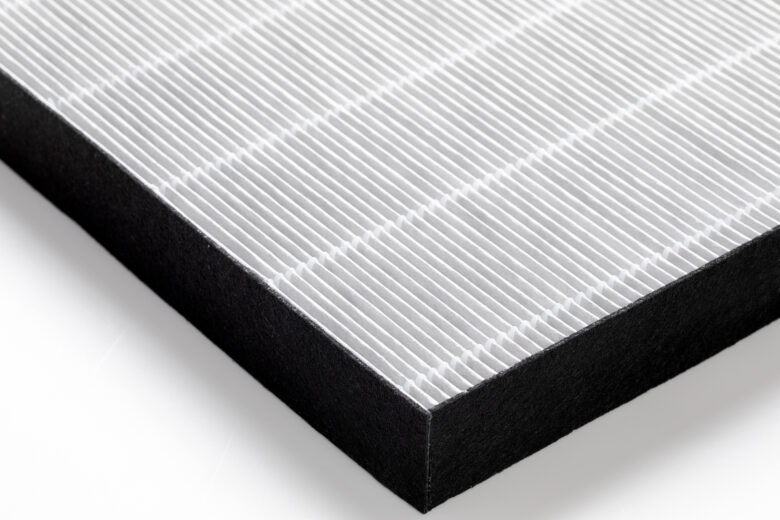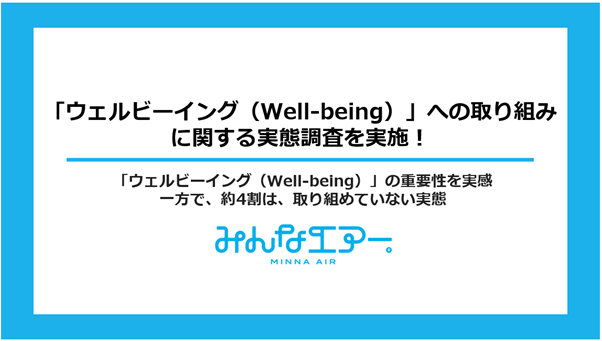北海道のお土産といえば「白い恋人」。誰もが知る北の銘菓を作っているのは、北海道を中心にお菓子の製造・卸しを展開する石屋製菓株式会社です。同社で製造した製品は石屋商事株式会社で卸小売しています。また石屋商事株式会社は白い恋人パークの運営・管理もしており、2社でISHIYAグループと呼称しています。また、サッカーJリーグの北海道コンサドーレ札幌、カーリングやバドミントンなど、北海道のプロスポーツチームを積極的に支援するなど、地域社会への貢献やスポーツ振興という点でも有名な企業です。
ISHIYAグループは企業理念でもある「しあわせをつくるお菓子」に基づいて、従業員が心身ともに健康であることを第一に考え、2022年に健康経営宣言を行いました。翌2023年には、健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定を受け、2024年には同認定の「ブライト500」、2025年には「ネクストブライト1000」にも選出されています。
今回は、人事総務部で社員の健康増進やメンタルヘルスの推進に取り組む柿村さん、須田さんのお二方に、健康経営®へのこれまでの経緯や今後の展望についてお話を伺いました。
「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
先を見据え 従業員の健康意識を高めていく

―――まず、御社の事業についてお伺いさせてください。
柿村:弊社の事業は北海道土産である「白い恋人」の製造・卸しをメインとしております。「白い恋人」の販売は基本的に北海道内の特約店様とグループ会社が運営する「白い恋人パーク」という札幌のテーマパーク内のみになります。このように弊社は地元北海道にこだわった事業を続けている会社です。
当社の中期経営計画のスローガンは、【 いつも北海道のそばに。 Stand By Hokkaido 】 と掲げ、北海道にもっともっと寄り添った企業となることをめざして、さまざまな取り組みを行っています。2023年に札幌以外では初の直営店を旭川にオープンさせたのもその一環です。また、道内各地域との接点を広げ、お菓子の原材料は、基本的に北海道の農畜産物ですので、供給してくれる道内の一次産業の課題にも積極的に関わっていこうと考えています。これからもこの取り組みを進め、北海道を原点としたブランドの強化を目指していきます。
―――健康経営の取り組みを始めたきっかけや目的を教えてください。
柿村:健康経営に取り組むきっかけとなったのは、実は…健康診断で従業員の血中脂質が全国平均よりも高いという結果からなんです。食品会社なので美味しいもの食べる機会が多いんですよ(笑)。当社の従業員の平均年齢は30歳代で、比較的若いということもあって、現状では健康上の課題がそれほど多いわけではないんです。でも、長く元気に仕事をしていくためには些細なことでも改善していかなければなりません。そこで、従業員の健康を維持・改善しながら会社の価値も上げていける健康経営に取り組んでみようということでスタートしました。
―――確かに、美味しいものに囲まれていますものね(笑)。
柿村:やはり全体的に若い人が多いせいか、どうしても健康に対する意識は高くはないんですね。不摂生しても、まあ大丈夫だろうって感じで。
須田:そうなんです。毎年、健康アンケートを従業員に実施しているのですが、有所見者率の割合に対して、“自分は健康だと思いますか”という問いに「健康だと思う」、「問題ない」という回答が多く、上回っていましたね。

―――健康経営の取り組みはいつ頃からスタートされたのでしょうか。
須田:私は2019年から人事総務部の健康診断の担当になったのですが、当時から血中脂質の所見率の高さは気になっていました。でも、会社としてどう対応するのか、というところまではまだいかなかったですね。
柿村:私が人事総務部に来たのが2022年で、前任者から健康面のこういうところが課題だということを引き継ぎました。改善を進めるのであれば、まずは皆さんの意識を高めることが必要だと思いまして、会社として“健康経営に取り組む”という目標を掲げた方が効果的ではないかと考えたわけです。
血中脂質の改善対策!社員食堂のメニューを大幅見直し

―――御社は2024年には健康経営優良法人の「ブライト500」に認定されています。取り組みをスタートさせる際に、どのような計画を立てられたんでしょうか。
柿村:課題だった従業員の血中脂質対策をはじめ、健康の基本となるのは“食事”ということで、食の改善に取り組みました。社員食堂のメニューを大幅に見直して、できるだけ身体に良い「健康増進メニュー」を提供することにしました。
須田:実は、社内での食事は社員食堂で提供されるもののみというルールがあります。食品会社ですので食中毒の発生に備えて原因食材がわかるようするためのルールですね。手作りのお弁当などはもちろん、他の食べ物の持ち込みもできません。ならば、この社員食堂のメニューをヘルシーな内容にすれば血中脂質対策にもなるし、健康的な食習慣づくりにもつながるはずだと。
たとえば、定食や丼もののご飯は白米と十六穀米を選べるようにして、小鉢メニューは野菜を中心に、サラダも飽きのこないように日替わりにするなどして野菜の摂取量を増やすようにしました。費用もできるだけ安くする努力をしてきました。健康的だと言っても値段が高いとお昼を我慢する人も出てきてしまいますからね。この取り組みで毎日のお昼ご飯が楽しみという人も増えたことが何よりうれしいです。
柿村:特にひとり暮らしの食事って、なかなか健康面までケアできませんよね。この取り組みを始めてから従業員のご家族からも安心だと評価をいただくようになったんですよ。
スポンサードするプロスポーツチームとの連携イベント

―――ご家族からの評価はうれしいですね。その他では、どんな取り組みをされましたか。
柿村:運動機会の創出ですね。過去の例になりますが 「部署対抗!ウォーキングイベント」を開催しまして、11チーム300名以上が参加して約2週間の期間中の総歩数を競うというものです。このイベントのために、「ひと駅分歩こう!」とやる気満々の従業員も出てくるなど、すごく盛り上がりました。
また、弊社がスポンサードしているプロスポーツチームと連携した運動イベントも実施しています。たとえば 「カーリング体験会」 がありまして、「北海道コンサドーレ札幌カーリングチーム」のプロ選手を講師にお招きして、従業員とご家族にカーリングを体験してもらうというものです。スキーやスケートとも違う氷の上を滑る運動で、参加者からは「普段使わない筋肉を使うスポーツで、とてもよい運動になった」と好評でした。初体験の方が多かったのですが、皆さんカーリングの楽しさを満喫していました。

須田:バドミントンを通じた運動イベントもありましたね。これも「北海道コンサドーレ札幌バドミントンチーム」のプロ選手をお招きして、従業員とご家族にバドミントンの体験会を開催しました。普段から実践できるトレーニングやバドミントンの基礎をプロ選手から学ぶイベントですが、小さい子から誰でも楽しめるスポーツなのでこちらも大変盛り上がりました。
従業員のモチベーションアップを狙った「ヘルシーポイント」

柿村:こういった運動や健康にもっと積極的になってもらうために、須田が「ヘルシーポイント」という仕組みを考えたんです。「ヘルシーポイント」は運動イベントへの参加やウォーキング1ヶ月で3万歩の達成などカラダを動かすアクションに向けたものの他、健康診断でA判定だった、健康診断の再検査を受けた、禁煙に成功!など、健康に関するさまざまな行動をポイントの対象にしていまして、貯まるとプレゼントがもらえるという仕組みです。
須田:社内は比較的に年齢層も若くて交流も多いので、集まって何か運動するきっかけを作ろうと考えたものです。「ヘルシーポイント」の利用率は現状でまだ2~3割ぐらいだと思います。もっとたくさんの人に使って欲しいと思っているんですけど、そこはこれからの課題ですね。
柿村:メンタル面では、不調の従業員を早期にケアするために「社内メンタルヘルス窓口」というのも設置しています。元々は外部に窓口を設けていたんですが、相談者が利用しやすいように社内にも作ることにしたんです。メンタル不調とまではいかなくとも、気軽に話せる場所や会社として対応できる組織があるということが安心感につながってくれるといいなと思っています。

―――会社が「健康経営をやるぞ!」となっても、なかなか動いてくれないとか、健康はプライベートなことなので構わないで欲しいとか、そんなケースもよく聞きます。健康経営を進める上でハードルになったことはありませんか。
柿村:面白がってくれている人が多いですよ。お昼休みにウォーキングをして1日2万歩を続けている強者たちもいるんですよ!こういう取り組みをきっかけに従業員同士の会話も増えて、社内コミュニケーションが盛んになったなという印象です。
なかなか難しいなという点では、喫煙ですかね。屋外に喫煙所を設置して、仕事の始まる前か後、もしくは休憩時間内だけということにしました。それで少しは減ったかなというところです。 もうひとつは紙タバコを禁止にして、どうしてもという人は電子タバコにしてもらったんですが、これはすんなり受け入れてくれました。
その理由は、社長を含めて経営層がタバコを吸わないメンバーに入れ替わったというのが大きかったですかね。 何しろ社長自ら号令をかけたわけですから、そこは「やるぞ!」と通しやすかったです。ただ、健康のことはプライベートだからという人も一定数はいますので、今はそこをちょっとずつ切り崩している感じですね。
―――当初の課題であった血中脂質の結果に変化はありましたか。
須田:本当にちょっとなんですけれど、下がりました。健康診断を担当してくださっている医療機関の方も、血中脂質はすぐに大きく下がるものではないとおっしゃっていたので、これからも継続して取り組んでいこうと思っています。
業務から職場環境まで、従業員から上がる年間1万6千件の改善提案

―――ここ数年、多くの企業が健康経営に取り組まれるようになりました。生産性の向上であったり、人材不足の対策だったり、理由はさまざまですが、御社の健康経営に対する目的を改めてお伺します。
柿村:「白い恋人」だけに、私たちは絶対にホワイト企業でなければなりません(笑)。いろいろありますが、私たちの事業を健全なかたちで持続していくためには、やはり働く環境の整備・改善は必要なんです。
これは健康に限った話ではないんですが、弊社に「改善提案」という制度がありまして、従業員からの提案を奨励しています。昨年だけでも従業員からの発案が1,600件近くあったんですよ。その改善案のおかげで、多くの業務効率が向上しています。
―――具体的な事例をお伺いできますか。
柿村:たとえば製造部門であれば、製造ラインに流れてくる商品を、それまでは人の手で整理していたんですが、従業員発案のガイドを設置することで、その現場の人員削減が可能になりました。
売上につながる工夫もありまして、これまで「お菓子作り体験」で受け入れられるお客様は30人くらいだったんですが、包装形態の工夫により、体験時間が短縮され、2倍~3倍のお客様に対応できるようになったという改善案もあります。
そうした業務の効率化によって、時間的なゆとりや人員の余裕ができたことで、有給の取得や残業の削減などが可能になっていきました。
―――提案を奨励したり、評価したりする仕組みがあるんですね。
柿村:業務上の改善提案で上がってきたものはすべて社長や取締役に報告して、提案者に直接「いいね」が社内のチャットツールを通じて送られます。また、良い提案には社員総会での表彰もあります。
毎月、こうした改善案の発表会を実施するんですが、製造部門であれば上がってきた100件くらいの改善提案をマネージャーが1件1件報告する会があるんです。それを社長と取締役がチェックして、良い案ならばどんどん現場に反映していけるようにしています。
―――現場の方々の意識がそこまで高いというのに驚きました。では、これから重点的に取り組んでいきたい課題はありますか。
柿村:健康診断の再検査の受診率をしっかり100%にしていきたいですね。もうひとつは健康意識をもっと高めていくことですね。健康に良くない生活習慣を改めないと、今は問題なくても不摂生を続ければ、いずれは病気になる可能性が高くなるといった意識付けのところです。
須田:意識付けの対策として、ひと月に1度ヘルシーレポートを出しています。そこで健康に関するタイムリーな情報や、春夏秋冬、季節ごとに特有のヘルケア情報などを発信しています。また、産業医さんにも会社に来ていただいて健康に関するレクチャーを実施していまして、これも健康意識を高める手助けになっています。
―――今後、健康経営の取り組みを通じて実現したいことは。
柿村:ISHIYAグループの企業理念は「しあわせをつくるお菓子」です。この理念をかたちにするには、まず、従業員の皆さんが心身ともに健康であることが第一です。私たちはこれからもより良い「健康経営」に向かって、改善を重ねていきます。また、弊社の従業員だけでなく、健康に関する事業活動を通じて地域社会の健康づくりにも貢献していけることを願っています。
<プロフィール>
石屋製菓株式会社 https://www.ishiya.co.jp/
人事総務部 柿村 俊子 須田 はるな