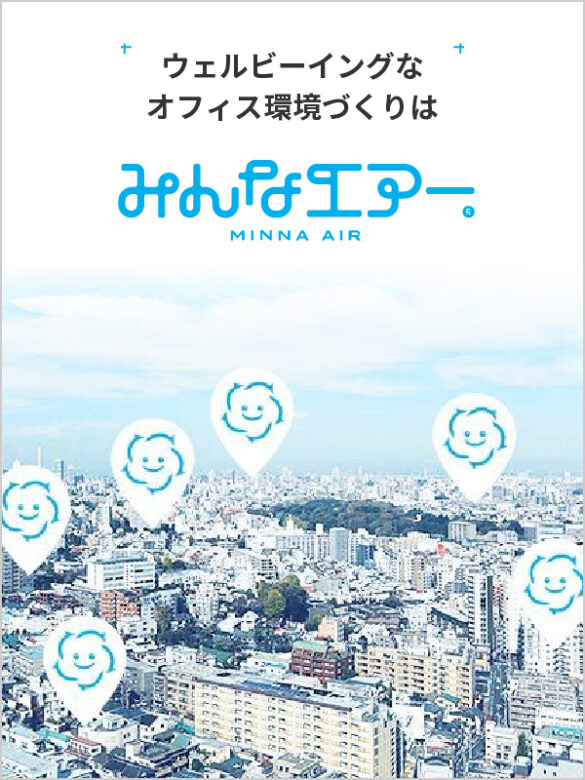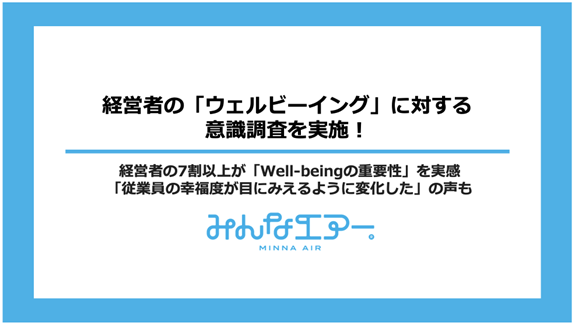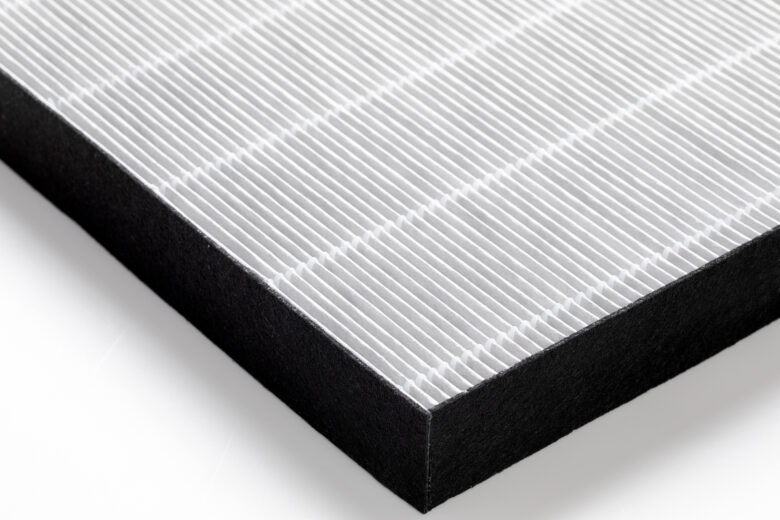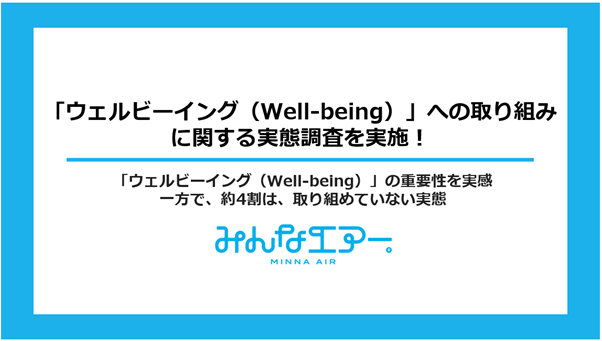この記事は、 7 分で読めます。
ノロウイルスが原因の感染性胃腸炎は、毎年11月から2月頃に流行する感染症です。保育園や幼稚園、学校、高齢者施設などで集団感染が発生するため、これらの施設ではさまざまな対策がとられています。
ここでは、ノロウイルスが学校で流行する理由と感染した場合はどうすればいいのか、予防対策として学校ではどのような取り組みが行われているのかについて解説します。
【みんなエアー】 仕事も生産性もアガル!空気のきれいな安心できる職場で
ノロウイルスが学校で流行する背景
ノロウイルスによる感染性胃腸炎が毎年学校で流行しやすい背景には、ノロウイルスの持つ特徴にあります。集団感染の原因となる主な特徴には、下記のようなものがあります。
感染力が強い
ノロウイルスは非常に感染力が強く、わずか10~100個程のウイルスが体内に入っただけで感染が起こります。
排泄物中のウイルス量が多い
ノロウイルスは感染者の下痢便や嘔吐物に含まれており、人の手や飛沫などを介して広まります。ノロウイルス感染者の嘔吐物には、1gあたり10万個前後、便には1gあたり多いときで約10億個のノロウイルスが含まれているため、手洗いが不十分で少しだけ手にウイルスが残っていたような場合でも、その手を介してウイルスが広まってしまうのです。
ウイルスが排出される期間が長い
ノロウイルスに感染すると、24~48時間の潜伏期間を経て、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、微熱などの症状が出ますが、多くの場合は1~2日で治まります。
しかし、症状が治まっても、1週間程は吐しゃ物の中にノロウイルスが含まれ、長ければ約1ヵ月はウイルスが排出され続ける場合もあるのです。その場合は、無症状なので気づきにくく、知らないうちに感染源になってしまう可能性もあります。
さまざまな感染経路がある
ノロウイルスの主な感染経路は、感染者の下痢便や嘔吐物に含まれるノロウイルスが、何らかの方法で口から体内に入ったことによる経口感染です。「ウイルスのついた手でドアノブや手すりにさわる」「ウイルスがついた手で料理をする」「感染者の吐しゃ物を処理した際に乾燥して空気中に舞い上がったウイルスを含む粉塵を吸い込む」など、さまざまな感染経路があります。
また、ノロウイルスに汚染された二枚貝などを十分に加熱せずに食べたり、ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道水を、消毒不十分で飲んだりした場合も感染につながります。
こちらの記事もおすすめ
ノロウイルスの感染経路別予防方法を、冬になる前に知っておこう!
アルコールで除菌できない
ノロウイルスはアルコール抵抗性が強く、アルコール消毒だけで十分な除菌を行うのは難しいという特徴があります。ウイルスを完全に不活性化する方法には、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒や加熱による処理が適しています。
ノロウイルスにかかったら学校はいつから登校できる?
ノロウイルスにかかると、発症から1~2日は吐き気や嘔吐、下痢、腹痛、微熱といった症状が出ますが、多くの場合は後遺症もなく、3日程過ぎれば快方に向かいます。では、症状が落ち着いた後は、いつから学校へ登校できるようになるのでしょうか。
学校は感染症の流行が起こりやすい場所なので、予防すべき感染症については「学校保健安全法」と「学校保健安全法施行規則」によって、細かく定められています。
ノロウイルス感染症は、これらの規定の中で「第三種の感染症として扱う場合もあるその他の感染症」という扱いです。「学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、校長が第三種の感染症として緊急的に措置をとることができるもの」とされています。
つまり、「条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患」のため、ノロウイルス感染症になっても、通常は出席停止にはなりません。
しかし、出席停止にならないからといって体調が戻らないうちに登校するのは、本人のためにも、周りにうつしてしまう可能性を高める意味でも好ましくありません。二次感染を防ぐため、再登校のタイミングは自分で判断するのではなく、医師の判断を仰ぐのがおすすめです。学校によっては再登校にあたり、医師による治癒証明書や登校許可届の提出が必要な場合もあります。
ノロウイルスの感染が疑われた場合
ノロウイルスには抗ウイルス薬はないので、対症療法が基本です。ノロウイルスの症状はほとんどの場合、2~3日もすれば治まるので、感染が疑われる場合、ひどい脱水や体力の消耗が見られないようなら自宅で療養し、回復するまでの数日間は当校を控えましょう。
療養中は脱水を起こさないように、水分摂取はこまめに行います。下痢止め薬は、病気からの回復が遅れる場合もあるので、医師の指示がない限り服用は控えましょう。
【みんなエアー】まだ、室内の空気、気にしてないの?空気の見える化は基本の「き」
学校側で実際に取り組んでいるノロウイルスの感染予防対策
感染力の高いノロウイルスの流行を防ぐため、学校ではさまざまな感染予防対策がとられています。その一例をご紹介しましょう。
汚物処理グッズの活用
ノロウイルスは下痢便や嘔吐物に大量に含まれており、そこから二次感染が広まることから、感染予防には汚物を適切に処理することが大切です。
使い捨てのガウン、マスク、手袋、ペーパータオル、消毒用の次亜塩素酸ナトリウム水などを備えた汚物処理グッズを活用、および職員が処理の仕方を周知し、二次被害の発生を防いでいます。
学校医による児童への指導
学校医による指導が行われているところもあります。児童がノロウイルスについての知識を持つことで、感染予防のための手洗い・うがいの徹底や、学校のトイレで下痢をした場合は担任に報告するといった指導が行き渡りやすくなります。
共用部の殺菌
ノロウイルスは、ウイルスのついた手で共用部のものをさわることでも感染が広がります。そのため、共用部のドアノブや階段の手すりなどを次亜塩素酸ナトリウム水で消毒することで、二次感染の予防につながります。トイレのドアノブや水道の蛇口、便器を定期的に清掃・殺菌することも有効です。
給食への取り組み
給食を通じての感染を防ぐため、罹患者のいる学級の食器は別扱いで洗浄・消毒を徹底する、配膳前の台ふきんの消毒に次亜塩素酸ナトリウム水を使うといった取り組みが行われています。
教職員による情報の共有
教職員がノロウイルスについての知識を持ち、学校全体の情報を共有することで、予防効果を高めています。
こちらの記事もおすすめ
ノロウイルスの特徴を知り、感染症対策を見直すことが予防につながる
ノロウイルス感染症を完全に予防することはなかなか難しいものですが、子供やその保護者、学校関係者の一人ひとりがノロウイルスに関する知識を持ち、集団感染を起こさないことを意識して行動することで、予防効果は高まります。
株式会社UPDATER ( 旧 みんな電力株式会社 )では、空気環境を可視化し、データの分析・通知・アフターサポートまで行うクラウドサービス「MADO」を提供しています。「MADO」は、室内の空気中に含まれる二酸化炭素やPM2.5、揮発性のガスといった物質を計測し、クラウドに送信。管理者のコンピューターやタブレットなどのデバイスに表示し、その空間の空気がどのような状態なのかを可視化できるため、換気やその他状況に応じた対策を行うことが可能です。